はじめに
『ロストシティ(Lost Cities)』は、数多くの名作を世に送り出してきたライナー・クニツィア氏による2人用カードゲームです。そのシンプルで洗練されたデザインは、初心者にも入りやすく、それでいて何度遊んでも飽きがこない奥深さを秘めています。
ルールは簡潔で、手番にはカードを1枚プレイまたは捨て、1枚引くだけ。しかしその中で「どの遠征に挑むか」「いつカードを出すか」「相手の意図をどう読むか」といった数々のジレンマと戦略的判断が求められます。
この記事では、海外の戦略サイトやコミュニティから得られた知見をもとに、初心者から上級者まで参考になる実践的な攻略法を段階的に解説します。
基本戦略の核心
1. カード枚数制限の理解
ロストシティ最大の特徴の一つが「22枚のプレイ上限」という、ゲームデザインに根差した隠れた制約です。実際のプレイでは気づかないこともありますが、この数字があなたの行動すべてに影響を与えるといっても過言ではありません。
- 配られるカードは8枚
- 山札には44枚
- よって、1ゲームで引けるカードの最大数は22枚
つまり、「あれもこれも」と遠征を広げてしまうと、どの遠征も中途半端な点数で終わってしまうリスクが高くなります。むしろ、プレイ機会が限られているからこそ、無駄な行動を徹底的に減らし、必要な遠征にリソースを集中させることが重要になります。
2. 最適な遠征数:3-4色戦略
全5色すべてに手を出すことは、理論的にも実戦的にも避けるべきです。ゲームの中盤以降に「あの色はやめておけばよかった…」と後悔することは、多くのプレイヤーが一度は経験する失敗です。
3色に集中することで、必要なカードが手元に集まりやすくなり、結果としてコンボも狙いやすくなります。また、リスクをとって4色を攻める判断も戦略の幅を広げますが、その場合は1色ごとの完成度をある程度犠牲にする覚悟が必要です。
数学的戦略分析
スコアリングの基本数学
ロストシティでは各遠征でカードを3枚以上プレイしなければ、点数をプラスにすることは難しい仕組みになっています。
- 1〜10までのカード9枚が各色に存在
- その合計点は54点、平均すると1枚あたり6点
- 投資カードを使うことで最大4倍になりますが、20点の初期コストがあるため、それを上回る成果が求められます
つまり、遠征ごとに最低でも20点を超えるスコアを出せるかどうかを見極めながらプレイする必要があります。逆に20点に届かなければ、その遠征はマイナスとなってしまうこともあるため、早い段階で損益分岐点の見積もりを行う力が重要です。
「ワンカードルール」
たった1枚の追加カードで損益分岐点を突破できる可能性があるか。これを見極める「ワンカードルール」は、シンプルながら極めて実用的な判断基準です。
たとえば、投資カードを2枚出し、5と7を持っている状況で、8以上のカードが引ける確率は82%。この期待値が高いと判断できれば、迷わず進むべきです。しかし、低確率でしか打開できない状況なら、一旦引いて再評価する冷静さも必要になります。
高度な戦略テクニック
1. 投資カードの効果的な活用
投資カードは一見強力ですが、使い方次第では自爆の原因にもなり得る、諸刃の剣です。単純に出すだけではなく、「どの色で出すか」「いつ出すか」「何枚出すか」の判断がすべて勝敗に関わってきます。
- 投資カード1枚だけでもリスクは大きく、慎重な判断が必要です
- プレイ前にその遠征で20点以上が見込めるかを冷静に評価すること
- 逆に、手札に強いカード(例:8・9・10など)が揃っているなら、2枚目・3枚目の握手カードを大胆に投資しても良い場面があります
序盤に投資カードを出すことで、相手にプレッシャーを与える「心理的優位」も得られることがありますが、あくまで勝算のある色に限定しましょう。
2. 小さな数字でのブラフ戦術
あえて価値の低い2や3のカードを捨てることで、相手に「この色は弱い」と思わせ、逆にその色の強力カードを放出させるという戦術です。
- 2や3の捨て札には大きな損失がないため、安全なブラフとして有効です
- 相手がその色の握手カードを出すよう誘導できれば、相手の得点を抑えることに成功します
- この戦術はあくまで「心理戦」であり、情報操作の一種です
ただし、使いすぎると本当に自分の選択肢が狭まるため、バランスが重要です。
3. 時間稼ぎ戦略
山札が少なくなってきた際に、1ターンでも多くプレイするための「時間稼ぎ」は、終盤に得点を爆発させるための大切なテクニックです。
- 山札が10枚を切ったら、毎ターン「カードを引く」こと自体が貴重になります
- 捨て札からカードを拾うことで、山札を消費せずに手番を回すことができます
- とくに「もうすぐ完成する遠征」がある場合、時間稼ぎによって1〜2枚の追加カードを引けるチャンスが生まれます
ただし、捨て札の内容を見極めないと、ただの無駄手番になるリスクもあるため、状況判断が不可欠です。
リスク管理とタイミング
捨て札の数学的コスト
1枚の捨て札には、目に見えないコストが隠れています。特に、必要なカードがまだ山札に眠っている場合、そのカードを引くまでの平均回数を考慮に入れなければなりません。
- 例えば、6種類のカードを山札から引くには、平均7回の試行が必要(-35点相当)
- 中盤では11枚のカードなら約4.5回の試行(-23点相当)
- 終盤において6枚のカードを期待するなら、3回の捨て札で済むこともある(-15点)
このように、「捨て札=悪」ではなく、時期によっては有益な選択にもなります。特に、終盤に期待値の高いカードが山に残っているとわかっていれば、捨ててでも回転を上げる価値があります。
「ダンプカラー」戦略
意図的に1色を犠牲にして、その色で-5〜-10点程度の損失を受け入れつつ、他の色の得点チャンスを広げるという高等戦術です。
- 例えば3-4-5のカードだけをプレイすれば、その遠征の得点は-8点になりますが、その分、山札を回転させ、より有益なカードを手に入れるチャンスが増します
- ダンプカラーで時間を稼ぎながら、別の遠征でボーナスの8枚達成を狙う、といった高リターンの布石になることもあります
この戦術は上級者向けですが、成功すれば勝敗を決定づける力を持っています。
相手への対策
1. カード拒否戦術
「相手の欲しいカードを与えない」戦術は、ロストシティにおける最も直接的な対抗手段のひとつです。特に、相手が投資カードをプレイしている色に関しては、その数字カードの扱いに最大限の注意が必要です。
- 相手が投資カードを出しているにも関わらず、後続の数字カードをなかなかプレイしない場合、それはカード待ちのサインかもしれません
- そのとき、相手が狙っているであろうカードを自分の手札で抱え続けることで、相手の手を封じ、焦らせることができます
- 特に有効なのは、4〜7あたりの「つなぎ役」のカードを止める戦術です
ただし、自分の戦略を犠牲にしてまでブロックし続けるのは得策ではありません。相手への妨害は、あくまで自分の得点が成立することが前提です。
2. ブロック戦術
ブロック戦術の応用として、「何を渡すか」の判断も極めて重要です。相手が投資カードを2枚出した色に対して、9や10の高得点カードを渡すのは非常に危険ですが、場合によっては逆に低い数字(2〜4)を渡す方が損害を与えるケースもあります。
- 例:投資×2(×3倍)状態で「3」をプレイさせると、+9点で済むが「9」を渡すと+27点になる
- つまり、カードを渡す=損失覚悟なので、渡すなら「最大限効果を削いだ形」で渡すように心がけましょう
実践的な判断基準
ゲーム段階別戦略
序盤(山札30枚以上)
- 複数の遠征を検討しながら様子見をする余裕がある段階です
- 低数字のカードや投資カードを活用しやすく、ブラフや捨て札もリスクが低い
- 手札調整と情報収集が大切です
中盤(山札15〜30枚)
- 遠征を3〜4色に絞り、重点的にカードを展開していくフェーズです
- この時期の捨て札は大きな損失につながることもあるため注意
- 相手の動向もより綿密に観察しましょう
終盤(山札15枚以下)
- 明確に目標を定め、確実にカードをプレイしていく段階です
- 高得点狙いの投資カードは基本的に使いどころを過ぎています
- 「山札があと◯枚」かを数えながら、終了ターンを逆算して計画的に動きましょう
期待値による判断
遠征開始時に「その色でどのくらい得点が見込めるか」の計算が重要です。
- 初期期待値 = 22点 +(現在のカード価値 × 0.6)
- たとえば、手札に「8」と「9」だけあれば、合計17×0.6 = 約10点、これに22を加えて期待値32点
- 投資カードが絡む場合は、この期待値に2倍・3倍を掛ける形で検討できます
期待値を算出しながら、「その遠征を本気でやる価値があるか」を常に判断するようにしましょう。
上級者向けテクニック
1. カウンティング
ロストシティは記憶ゲームではありませんが、「すでに出されたカード」を記憶しておくと非常に有利になります。
- たとえば、すでに6〜10のカードがプレイされている色では、今後の引きで高得点を望めません
- また、相手が6を捨てたとき、それがどれだけ残りの選択肢に影響するかを即座に把握できるようになります
完全記憶を求められるわけではありませんが、「4はもう3枚出たな」程度の意識でも大きな差になります。
2. 心理戦
相手のプレイスタイルや癖を読み取り、それに対して柔軟に戦術を調整することも重要です。
- 序盤から握手カードを多く出すプレイヤーには「強い色ブロック」
- 捨て札を頻繁に拾うプレイヤーには「カード回転を妨害する」ような動き
- 相手が消極的なプレイをしていると感じたら、やや強気に展開してプレッシャーをかける
「読み」と「揺さぶり」は、経験値が増えるほどに鋭さを増していきます。
まとめ
ロストシティは、ただの「2人用カードゲーム」ではありません。確率・記憶・心理・リスク管理といった多彩な要素が組み合わさった、非常に深みのある名作です。
勝率を高めるために必要なポイントは以下の5つです。
- カード22枚制限の理解と意識
- 3〜4色に集中する計画性
- 期待値に基づく冷静な判断
- 捨て札や握手カードのタイミング管理
- 相手の行動を読み、必要に応じて妨害する柔軟さ
これらを実践していけば、ロストシティの魅力を最大限に引き出しつつ、コンスタントに勝利を掴めるプレイヤーに成長できるはずです。
参考文献
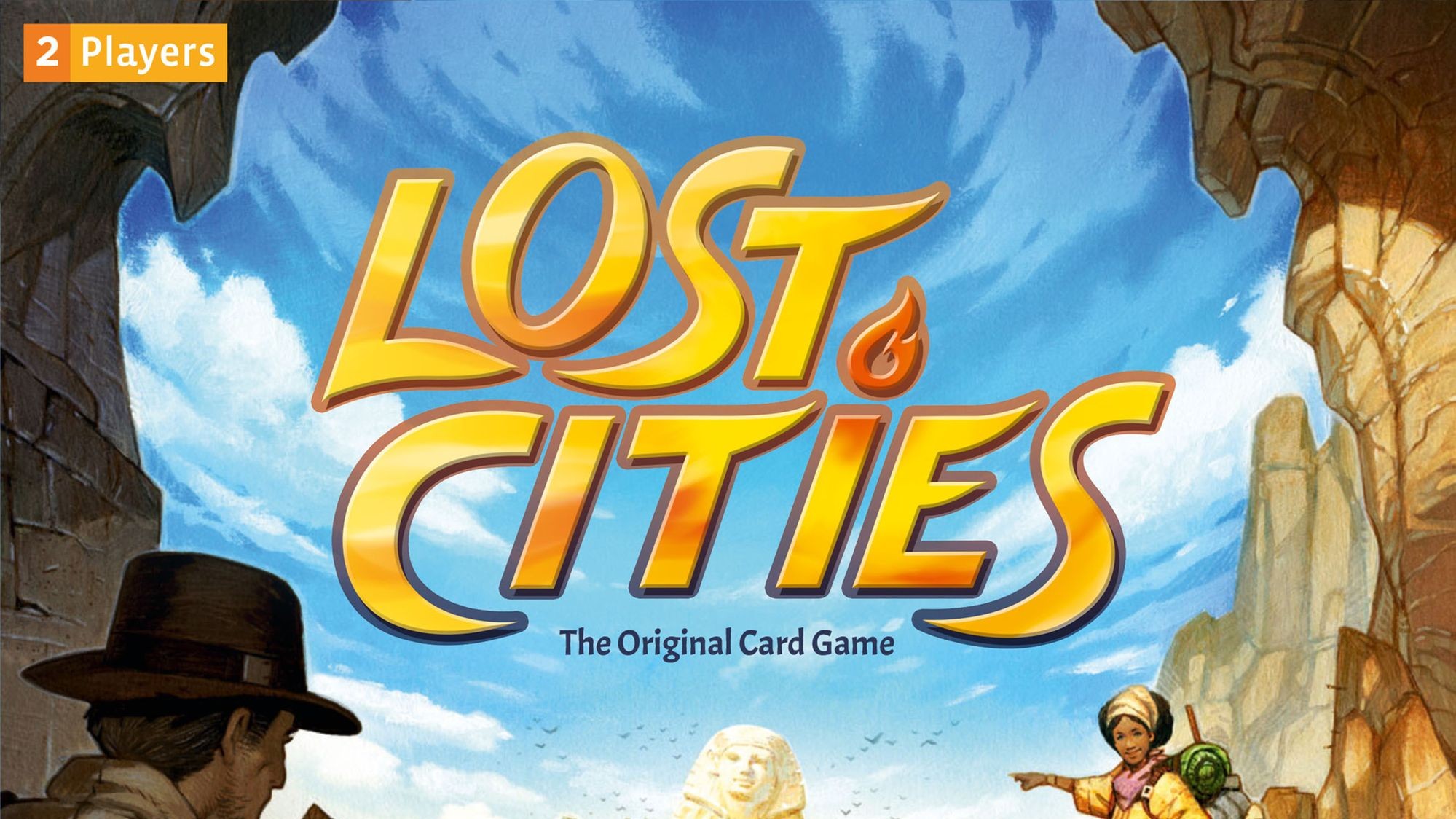


コメント